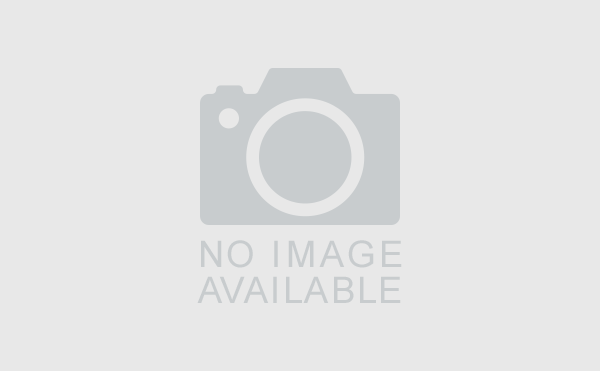胚培養士養成の難しさ
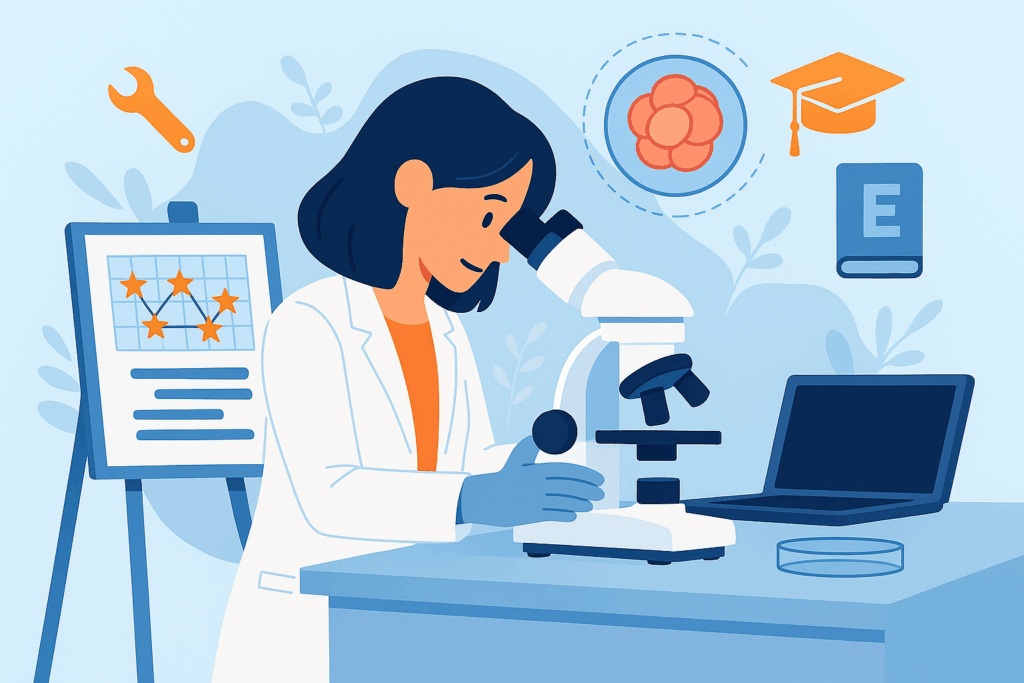
今日は、弊社が関わる分野のひとつ、「胚培養士(エンブリオロジスト)」の養成について、少し深掘りしてお話ししたいと思います。
高度生殖補助医療(ART:Assisted Reproductive Technology)は、2022年の保険適用や政府の少子化対策を背景に、今後ますますニーズが高まる分野です。参考:日本産科婦人科学会の情報 / 厚生労働省公式サイト。
ですが、その治療を支える「胚培養士」の人材育成については、業界内でも根深い課題があると認識されています。
現在、胚培養士になるための「国家資格」や統一された教育課程は存在していません。そのため、「誰が・どこで・どのように育てるか」は施設ごとに大きく異なり、個人の経験や現場のOJTに依存するのが現状です。
さらに、養成にあたっては以下のような課題があります
- 出身分野が多様(医学・農学・生物系など)で、知識にばらつきがある
- 技術の習得に時間がかかる(ミスが許されない領域)
- 施設ごとに方針や文化が異なる
- 業務の負荷が高く、離職率が高い
これらは、人材が定着しない → 教育が継続できない → 技術の継承が困難になるという、負のスパイラルにつながるリスクをはらんでいます。
弊社では、こうした現場の声に応え、以下のような取り組みを行っています
- 効率的で実践的な新人研修プログラムの開発
- いつでも学べるE-learningプラットフォームの整備
- リアルな現場を模したトレーニングツールの開発
- 技術レベルの可視化と評価支援(スキルマップ等)
これにより、「誰でも、どこでも、一定のレベルで学べる環境」の実現を目指しています。
不妊治療の技術や患者ニーズは、これからも変化していきます。それに対応できる胚培養士を、どう育て、どう支えていくか――それは業界全体の課題であり、私たちが真剣に取り組むべきミッションだと考えています。
私たちの取り組みが、少しでもこの課題の解決に寄与できればと願っています。